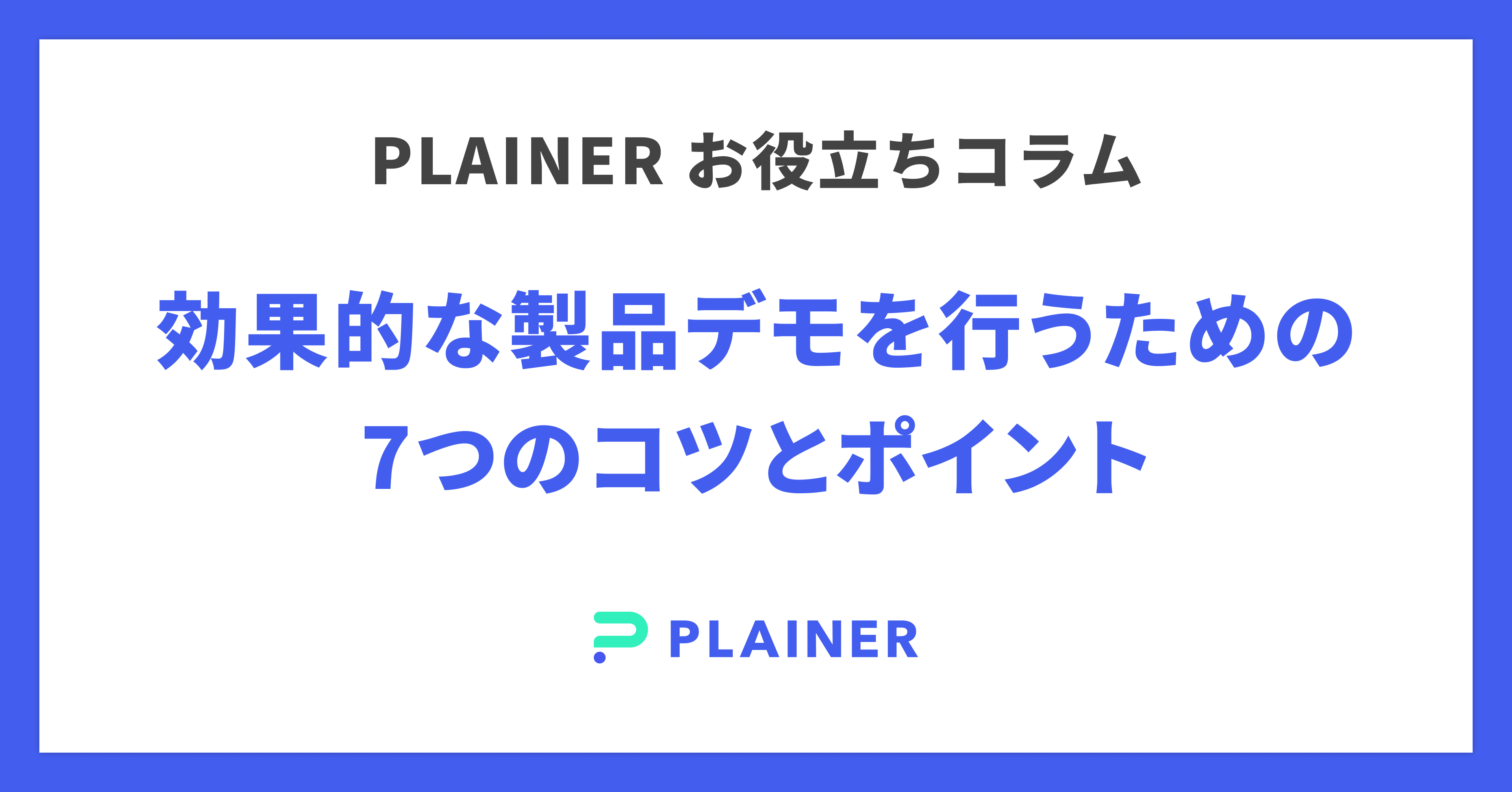効果的な製品デモを行うための7つのコツとポイント
製品デモは、マーケティング活動、営業活動、顧客のエンゲージメントを高める活動として、クラウドサービスのベンダーを始め、多くの企業で実施されています。
しかし、製品デモに苦手意識を感じている営業パーソンは少なくありません。
今回は、顧客の期待を超える製品デモを行うためのコツやポイントについて紹介します。
製品デモとは?
製品デモとは、企業が製品やサービスの使い方を実演や動画で顧客に分かりやすく説明することです。
特に、機能や価値が伝わりにくい無形商材において、製品デモはプロダクトの価値を効果的に伝える手段として多くの企業で実施されています。
製品デモは、単なる製品説明ではなく、顧客のニーズや状況に応じた情報を伝えることが重要であるため、コツやポイントを押さえて、準備をすることが重要です。
【関連記事】製品デモとは?重要性や効果、成功させるポイントを紹介
製品デモを改善することで得られる効果
コツやポイントを押さえ、製品デモを改善していくことで得られる効果を紹介します。
顧客の製品理解の促進
製品デモを効果的に行うことによって、テキストや画像のみで製品を訴求するよりも製品についての理解を深めてもらえます。
特に無形商材のものは、製品導入前には操作イメージを持ちづらいため、製品デモの重要性は非常に高いです。
受注率の向上
製品の理解を促進するとともに、機能や価値の理解が深まることで、導入にあたっての不安や懸念点が払拭でき、受注率の向上が期待できます。
特に製品デモをコンテンツ化し、その企業向けの製品デモコンテンツを用意できると、顧客がタイミングを問わず自由に操作確認ができるため、より製品への理解が深まり、さらなる受注率の向上に期待できます。
セールスプロセスの効率化
商談の中で製品デモを実施したり、製品デモのコンテンツをマーケティング活動から営業活動内で活用することによって、見込み顧客発掘から導入に至るまでのプロセス内の各種指標が改善され、セールスプロセスの効率化に繋がります。
導入後のミスマッチの減少
製品デモを実施・改善し、製品導入前に機能や活用方法などを理解してもらうことで、製品導入後に、「想像していたものと違った」という理由での解約件数を減少させることを期待できます。
関連記事:顧客に刺さる製品デモコンテンツの作り方やポイント、作成の流れを紹介
聞き手が製品デモに期待すること
聞き手である顧客が、製品デモに期待することを紹介します。
テキストや画像で得られない情報を得たい
デモの聞き手である顧客が製品デモに一番期待することは、サービス紹介資料や製品紹介では知りえない情報を得たいということです。
製品の導入後を想定して、ログインの仕方やダッシュボードの見方、普段使用する機能の使い方など、テキストや画像では得られない情報を得たいというのが一番求められることです。
製品の特徴を知りたい
続いて、顧客が製品デモに期待することとしては、製品の特徴が知りたいというのがあります。
現在は、同じカテゴリに似たようなツールが沢山あるので、その製品ならではの特徴を、デモを通して理解できることを期待しています。
UI/UXを知りたい
製品デモを通して、自分を含めた社内でその製品を使いこなせるのか、ストレスを感じにくいかなどを知りたいというニーズも大きいです。
特にその製品は、自分以外も使用するツールであれば、ITリテラシーが低くても使いこなせるのかというのは非常に重要なポイントですので、デモの重要性も高いです。
他社製品との違いを知りたい
複数の製品のデモを実際に操作をしてみて、他社製品との使い方や使いやすさの違いについて確認したいというニーズもあります。
同カテゴリの製品で解決できる課題は同じであっても、それぞれの製品で何が違うのか、いくつかの製品デモを確認して確かめた上で比較する方もいます。
営業が製品デモを上手く行えない理由
営業が製品デモを上手く行えない理由としてよくあるものが、「一方的に機能を説明すれば良いと思っている」「そのお客様に適したデモの準備していない」「製品への理解が不足している」ことなどが挙げられます。
総じて、営業自身が製品デモの重要性をきちんと理解しておらず、必要な準備や対策を行わないからこそ、製品デモを上手く活用できていない営業が多いです。
そのため、営業組織において製品デモを強化する際には、個々のデモのスキルを上げるとともに、営業組織全体で製品デモをより効果的に行っていくための仕組み作りの両軸で行うことが求められます。
関連記事:製品デモコンテンツを作成するのにおすすめの専用ツールとその特徴を紹介
製品デモを行う上でのコツ・ポイント
製品デモを行う上でのコツやポイントを7つ紹介します。
まずは製品デモの目的やメッセージを整理する
製品デモを行う前に、誰に何を伝えるのかという目的やメッセージを整理することが必要です。
どれくらいの時間で、どの順番で何を伝えると効果的なのかを考えて設計することで、より良い製品デモを行うことが可能です。
ただ製品紹介をすれば良いという考え方から脱却し、目的やメッセージに合わせてカスタマイズするという考え方で準備してください。
顧客に合わせたデモを行う
顧客ごとに製品デモに期待することや、抱えている課題、その担当者の状況が異なります。
そのため、その顧客に合わせて製品デモの内容をカスタマイズして実施することで、より高い効果を発揮します。
説明の順番や内容、伝え方を変えるだけで、製品デモの効果は変わります。
製品デモを行う前に導入を入れる
製品デモをいきなり行うのではなく、デモの目的やどこを具体的に見て欲しいのかなどをお伝えすることで、顧客もデモを受ける準備が整います。
また、適宜質問をしてくださいと事前にお伝えしておくことで、途中で疑問に感じたことをその場で解消でき、両者にとって良い時間になります。
デモのシナリオを用意する
製品デモを行う前に、あらかじめ、最終的なゴールに至るまでにどのような流れで進めるのかというシナリオを用意しましょう。
必ずしもデモのシナリオ通りに進めなければいけないということではなく、顧客の反応や対話を行いながら、進めていくのが重要です。
機能だけでなく価値も合わせて伝える
製品デモにおいては、特に「価値」を伝えることが重要です。
例えば、「このボタンを押すことで、〇〇の機能が利用できます」だけではなく、「この〇〇の機能を利用することによって、□□様がこれまで課題に感じられていた作業をクリック1つで完了でき、約〇時間の作業時間軽減に繋がります」といったような、時間短縮・コスト軽減・人為ミス軽減などの軸で価値を伝えると、より顧客に刺さるデモになります。
顧客とコミュニケーションを取りながら進める
製品デモは一方的に説明をするのではなく、顧客にオープンクエスションで質問して回答をもらうなど対話しながら進めることで、それまでの商談では引き出せなかった課題や要望などを引き出せる可能性が高まります。
体験できるデモコンテンツを用意する
最近では、海外を中心にインタラクティブデモと呼ばれる、製品の操作を本番環境とは別の環境のブラウザ上で体験できるWebコンテンツを活用する企業が増えています。
これが「体験できる製品デモコンテンツ」です。
顧客自身がこの体験できるデモコンテンツを操作することによって、知りたい情報を自分のペースで知ることができ、製品導入の検討度合いが高まることを期待できます。
関連記事:インタラクティブ動画とは?メリットや作り方、作成のポイントを紹介
PLAINERを活用して、製品を効果的に紹介するデモコンテンツを作成しませんか?
今回は、製品デモを重視する顧客の期待を超える製品デモを行うためのコツやポイントなどを紹介しました。
特に最後に触れた体験できる製品デモンストレーションのコンテンツは、マーケティング活動や営業活動、CS活動などあらゆるシーンで活用できます。このようなデモコンテンツを国内で唯一作成できるサービスとして、「PLAINER」が挙げられます。

PLAINERは、誰でもノーコードでソフトウェアを複製・カスタマイズしたデモコンテンツを制作し、顧客への提供とアクセス解析を可能にするサービスです。
サービス開始からfreee、Chatwork、ヌーラボなどの上場企業を含め、先進的なプロダクトを持つSaaS企業を中心に導入され、作成されたデモは10万人以上のユーザーに閲覧されています。
プロダクトの画面をキャプチャするだけで誰でも簡単に製品デモを制作できるので、これまで製品デモの制作や管理にかかっていた工数を大幅に削減できます。
製品デモをこれから制作を考えている企業様、製品デモの制作や運用に課題をお持ちの企業様は、ぜひサービス紹介資料をダウンロードいただくかお問い合わせください。